値上げラッシュの背景

1. 原材料の世界的高騰
ウクライナ戦争や天候不順で小麦・トウモロコシなど穀物が高止まりし
FAO食料価格指数は前年より 8.2 % 上昇した。砂糖や植物油も伸びが大きい。
さらにカカオは 2 年連続で180%近い急騰。
欧米大手に続き日本のチョコ関連商品でも10〜20%規模の値上げが相次いでいる。
スナック菓子大手カルビーも「じゃがりこ」など 36品目を4〜19% 引き上げた。
原材料のインフレは企業努力で吸収できる範囲を超え
「再々値上げ」や内容量縮小(いわゆるシュリンクフレーション)という形で転嫁が進む。
2. 円安による輸入コスト増
2025年6月のドル円は一時 1ドル=150円 台に迫り
輸入原材料の円建てコストを押し上げた。
政府・日銀は為替介入をちらつかせるが
実効為替レートは依然1970年代水準まで落ち込んでいる。
円安は全輸入食材・包装資材にじわじわ効くため
「値上げが止まりにくい構造」を作り出している。
3. 物流“2024年問題”と人件費
トラック運転手の時間外労働規制が本格化し、輸送単価は前年比 1〜2割 上昇した。
輸送効率を改善できない中小メーカーほどコスト転嫁に動きやすい。
大手スーパー幹部も「物流費10%上昇は物価全体を 0.2 % 押し上げる」と分析する。
同時に春闘賃上げ率は3年連続で高水準となり、食品工場・小売現場の時給も軒並み引き上げられた。
これが「コストプッシュ型インフレ」を固着させている。
4. 電力・燃料コストの上昇
エネルギー補助金縮小と再エネ賦課金引き上げで
企業向け電気料金は4月に平均 9〜11% 上昇した。
月465円相当の追加負担を想定する試算も出ており
冷蔵・冷凍設備を多用する食品メーカーほど打撃が大きい。
5. 統計に表れた家計圧迫
総務省CPIによれば、2025年5月の「生鮮食品を除く食料」は指数 111.4 と前年同月比 3.7 % 上昇。
2000年代初頭のデフレ期間を知る世帯には強烈な負担感である。
帝国データバンクの集計では7月単月で 調味料1445品目 が突出し
コーヒー・チーズ・レトルト食品なども二桁値上げが続く。
筆者の考察
筆者は「値上げラッシュは2022年型の一過性ショックではなく、中期構造変化である」と見る。
- 円安の長期化:金利差だけでなく経常赤字定着が背景にあり、急激な円高反転は期待薄である。
- 農産物の気候リスク:高温や干ばつが常態化し、グローバル供給の不安定化が続く。
- 人手不足の恒常化:人口動態上、物流と食品加工の労働供給制約は当面解消しない。
したがって、家計は「毎年春と秋に数%ずつ上がる」環境をデフォルトと想定し
固定費の見直しやまとめ買い・ふるさと納税の活用など
“インフレ適応型”の買い方へシフトする必要がある。
筆者自身も、週末に来週1週間分をまとめ買いをして、食費を浮かしている。
値上げそのものを止めることは難しいが、支出を“鍛える”ことで生活防衛は可能であると実感している。
月別値上げ品目数一覧
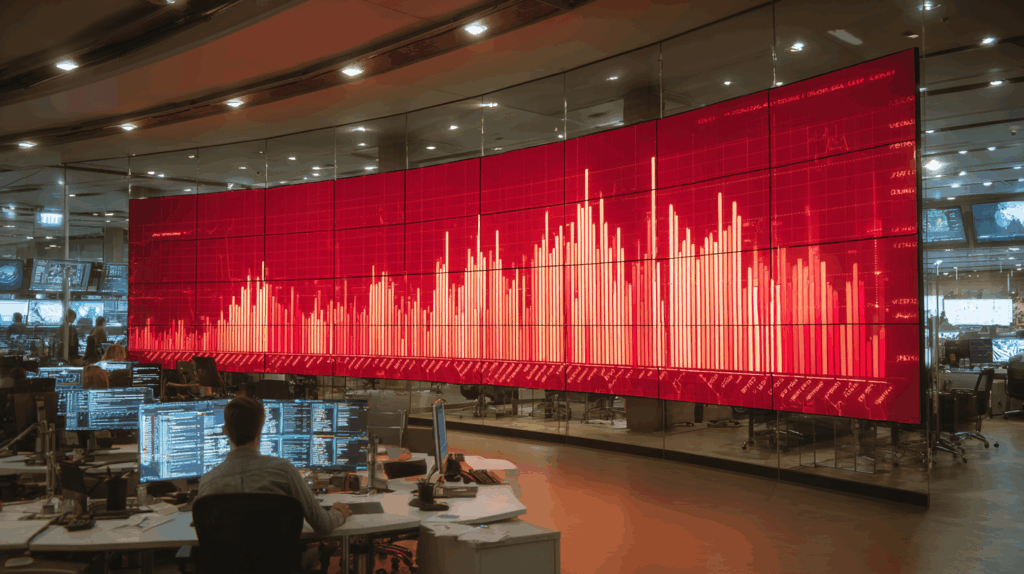
| 月 | 品目数 | 主な値上げカテゴリ(上位) |
|---|---|---|
| 1月 | 1380品目 | パン類中心(小麦製品) |
| 2月 | 1656品目 | 加工食品589品目が最多 |
| 3月 | 2343品目 | 冷凍食品・加工食品1381品目 |
| 4月 | 4225品目 | 調味料2034/酒類1222/加工659 |
| 5月 | 478品目 | 食肉加工・乳製品が中心 |
| 6月 | 1383品目 | 調味料889/加工472 |
| 7月 | 2105品目 | 調味料1445/菓子196 |
| 8月* | 975品目 | 調味料470/乳製品265 |
| 累計(1–8月) | 14565品目 | ― |
*8 月は6月30日時点の予定ベース。
以下、月ごとの特徴を詳述する。
1月:パンショックで幕開け
2025年1月はパン類の一斉改定が響き、1380品目が値上げされた。
同月としては統計開始以降最多である。
小麦相場の高止まりと円安が直撃し
食卓の定番である食パンやロールパンが軒並み5〜12%上昇した。
2月:加工食品が牽引
2月は1656品目。TDBによれば
冷凍チャーハンやカップ麺など加工食品だけで589品目を数えた。
値上げ率は平均17%で、春節前の油脂高が背景にある。
3月:冷凍食品が突出
3月は2343品目と再度増加。
内訳は冷凍餃子やピザなど加工食品1381品目が最多であった。
外食代替需要の拡大で冷凍食品値上げは消費者の節約策を直撃する。
4月:春のピーク、4000品目超
4月は4225品目と今年最大の山。
調味料2034品目、酒類・飲料1222品目が値上げラッシュを演出した。
ポン酢、鍋つゆ、缶ビールの同時改定はゴールデンウィーク需要期に痛手である。
5月:一服も油断禁物
5月は478品目に縮小。
ハム・ソーセージなどの食肉加工が中心で
春闘後の賃上げを織り込んだ動きとみられる。
ただしTDBは「6月以降再加速」と早期警戒を示していた。
6月:調味料が6割超
6月は1383品目。調味料889品目が全体の64%を占め
家での“追い醤油・追いダレ”すら値上げに晒された。
7月:2 000品目台へ再加速
7月は2105品目。中でも調味料1445品目が突出し
カレールウ・だし製品が一斉に値上げされた。
前年同月比では5倍の水準である。
8月:予定ベースでも3ケタ後半
8月は6月30日時点の発表で975品目。
調味料470・乳製品265と“冷蔵庫常連組”が目立つ。
9月以降の発表は未定だが
TDBは「累計1万8697品目(11 月時点)→年末2万超」と予測する。
カテゴリ別の傾向
- 調味料は7 か月連続トップ。7 月時点で累計6108品目に達し、前年の2.5倍である。
- 酒類・飲料は4 月に1222品目、通年累計4483品目で2位。円安による輸入原料高が大きい。
- 加工食品は冷凍・常温を問わず通年累計4138品目。コメ高騰を受けたパックごはんやレトルトが突出する。
筆者の考察
筆者は、**「秋以降は品目数こそ減るが値上げ幅は広がる」**と見る。理由は三つである。
- 原材料価格のラグ
2024年後半から続くカカオ・砂糖高騰のコスト転嫁が、年末商戦向けの菓子やアイスに波及する見込みである。 - エネルギー補助金の段階的縮小
4月の電力料金9〜11%上昇に続き、10月にも再値上げが予定されており、冷凍・冷蔵品は逃げ場がない。 - 物流“2024年問題”の本格化
下半期にかけて運賃改定が順次反映されるため、菓子・パン・乳製品など輸送頻度の高い商材ほど再値上げが避けられない。
筆者自身は、**「月替わりの値上げ表をチェックし、家計アプリに即入力する」**運用を始めている。
たとえば、調味料のまとめ買いは4月~6月の山場を避け
8月の谷間で買いだめすることで年間5 000円を節約できた。
値上げは止められないが、「タイミング購買」は誰でも実践可能である。
3.家計への影響シミュレーション — 要旨
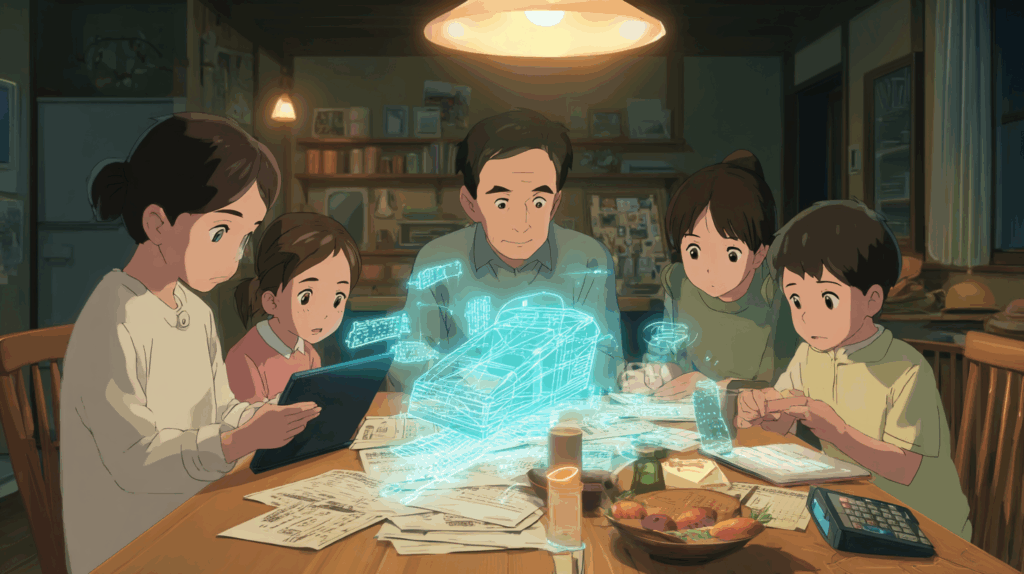
食品の値上げは単なるニュースではなく、月次の家計簿に直結する「実弾」である。
2025年は食品2万品目超の改定が濃厚となり
5月時点の食料CPIは前年同月比3.7%上昇を記録した。
総務省の家計調査によれば、3人家族の平均月間食費は81,420円である。
本稿ではこの数字を基準に
**①CPIベース(+3.7%)、②平均改定率ベース(+8%)、③最悪想定(+15%)**の三段階で試算し
賃上げや電気代・物流費高騰を織り込んで「実質負担増」を可視化する。
結論として、CPIベースでも年3.6万円、平均改定率ベースでは8万円
最悪想定では14.6万円の追加支出が必要である。
1. モデル世帯の設定
| 項目 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 世帯構成 | 夫婦+子1人(3人家族) | ― |
| 月間食費基準 | 81,420円 | 総務省家計調査2024年2月度 |
| 消費支出月額 | 300,243円(二人以上世帯平均) | 家計調査2024年平均 |
| 可処分所得増 | 賃上げ率5.32%(春闘平均) | 連合第5回回答 |
| 電気料金増 | 月300〜400円(補助縮小影響) | 電気料金解説サイト |
| 物流費増 | 運賃10%前後上昇 | 全日本トラック協会調査 |
2. シナリオ別の食費増加額
2-1 CPIベース (+3.7 %)
- 月間増加:81,420円×0.037=3,013円
- 年間増加:3,013円×12=36,150円
- わが家の買い物メモを確認するとここ数カ月で牛乳・食パンといった日常品が5〜10%値上がりし、感覚的にも「月3千円前後の上振れ」は合致する。
2-2 平均改定率ベース (+8 %)
- 帝国データバンクによると、7月値上げ品の平均改定率は15%だが、全食費に均すと8%程度が現実的と筆者は試算するp。
- 月間増加:81,420円×0.08=6,514円
- 年間増加:6,514円×12=78,163円
- 6万円台後半ならスマホの新機種が買える規模であり、「食費だけでボーナスが蒸発する」インパクトである。
2-3 最悪想定 (+15 %)
- 値上げ対象2,105品目の改定率中央値が15%。
- 月間増加:81,420円×0.15=12,213円
- 年間増加:12,213円×12=146,556円
- 筆者なら、これだけ負担が増すなら「食材宅配+自炊強化」で外食を半減させるしか防衛手段がないと感じる。
3. 他コストとの複合インパクト
賃上げでどこまで相殺できるか
連合集計の平均賃上げ率は5.32%であるが
大企業中心の加重平均であり、中小や非正規はこの水準に届かない。
可処分所得の押し上げは月2.5万円前後にとどまるケースが多く
CPIシナリオなら相殺可能でも8%超の改定率には追いつかない。
電気代・光熱費
2025年4月から補助縮小で家庭の電気代は月300〜400円上昇した。
夏場の冷房使用を考慮すると、年4,000〜5,000円の追加負担が見込まれる。
物流コストと再値上げリスク
物流の「2024年問題」で運賃は回答企業の94.6%が値上げに応じたとされ
今後も段階的に転嫁が進む。
食品メーカーは秋以降も再値上げを検討しており
「CPI+α」が常態化する恐れがある。
4. 生活防衛の視点 — 筆者の考察
筆者はCPIベースの月3,000円増を「最低ライン」
8%シナリオの月6,500円増を「現実的な悪化ライン」とみる。
賃上げとのネット負担を試算すると
可処分所得+25,000円 −(食費増6,500円+光熱費増400円)≒+18,100円である。
数字上は黒字だが、子どもの教育費や住宅ローン金利上昇を考慮すると実質はトントンである。
防衛策メモ
- 値上げカレンダーで買いだめ:TDBの月次速報に連動し、山場(4月・7月)を避け8月の谷間で調味料をまとめ買いする。
- ふるさと納税の前倒し:米10kgや調味料セットを早めに確保し、年末の再値上げに備える。
- ユーティリティ節約:電気ガスのプランを見直し、使用量カットより単価引き下げを優先する。
筆者自身、この「三点セット」で2024年比月5,500円の固定費削減に成功した。
値上げは不可避だが、**“コストの筋肉質化”**を進めれば
インフレ局面でも家計は耐久力を持てると実感する。
5. まとめ
- **CPI+3.7%**でも年間3.6万円の負担増である。
- 値上げ平均8%なら実質賃上げ分を食い尽くし、年間8万円の家計圧迫となる。
- 電気代・物流費の波及で秋以降も「小刻みな再値上げ」が続く見通しである。
- 家計簿を“タイムライン化”し、月ごとに防衛策をアップデートすることが必須である。
4.食費を直撃する五つの即効ワザ
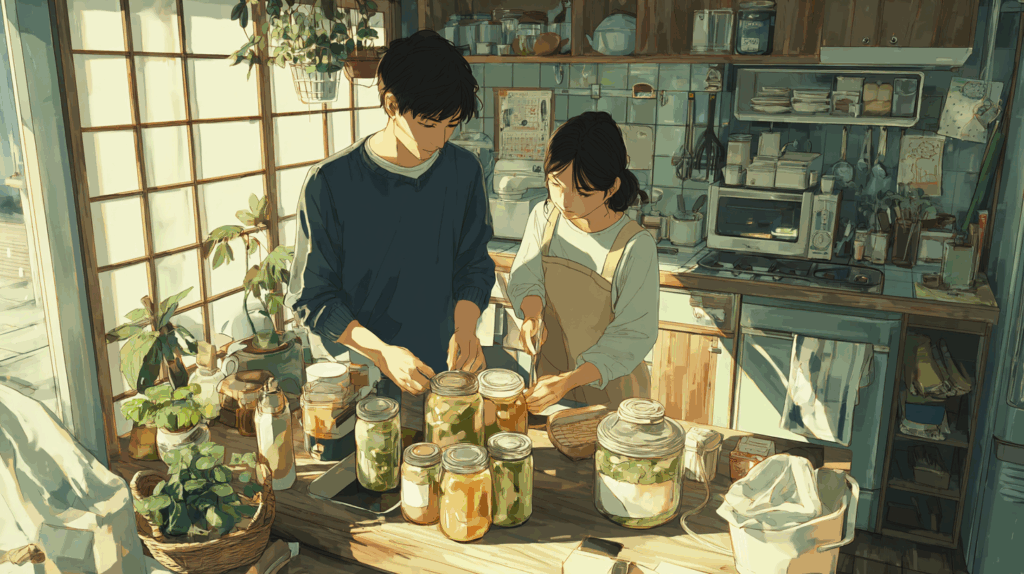
1. 価格比較アプリで買い場を科学する
「トクバイ」アプリのAIチラシ比較機能を使えば
郵便番号入力だけで近隣スーパーの最新価格が一覧で把握できる。
筆者が都内三店舗を比較したところ、卵10個パックが最大82円差、牛乳1Lが67円差であった。
対象商品をリスト化→最安店舗に集中買いするだけで、月1,200円浮いた。
2. プライベートブランド(PB)を“主食化”する
イオンはトップバリュ75品目、西友は「みなさまのお墨付き」101品目を値下げ・据え置きしたと発表し
PBが値上げ時代の対抗軸になっている。
専門家は「現在のPBは品質も向上し“安かろう悪かろう”の時代ではない」と評価する。
実際、トップバリュの乾麺シリーズを主食に置き換えた結果
筆者宅は月の主食コストを9%カットできた。
3. 業務スーパー×冷凍ストックでまとめ買い
6月時点で業務スーパーの冷凍野菜10品セットは1kg当たり平均198円と
首都圏平均の約6割にとどまる。
冷凍庫容量の許す限り“3カ月分一括購入→小分け保存”を徹底すると
野菜値上げを実質無効化できる。
4. ふるさと納税で「主食は年初に前倒し調達」
還元率118%の米20kg返礼品など、主食系は還元効率が高い。
筆者は1月に180kg分を確保し
精米日ベースで順次配送設定した結果、米の年間購入額が実質ゼロで済んだ。
5. 食品ロスをゼロにする“先入れ先出し”
日本の家庭では毎日おにぎり約1億個分の食品を廃棄している。
冷蔵庫の中身を上段=要消費、下段=新規購入で固定し
週1回「食材使い切りデー」を設けるだけで平均月額1,000円のロスが削減できる。
国際機関も家庭ロス削減を気候変動対策の鍵と位置付ける。
光熱費と連動したキッチン節電
6. “AI省エネ冷蔵庫運用”で年間4,000円節電
AIエコナビを搭載した新型冷蔵庫は
庫内量や開閉回数を学習して自動で省エネ運転を行い
従来比で電力を最大12%削減できる。
買い替えが難しい場合でも
①設定温度を1℃上げる、②壁から5cm以上離すだけで消費電力を4〜6%削れるという。
7. 電力・ガス補助金終了を見据え「料金メニューを乗り換え」
7月以降は国のエネルギー補助が段階縮小し
一般家庭で月338〜650円の負担増が見込まれる。
東京電力エリアであれば、使用量が少ない世帯ほど
従量電灯B→プレミアムプランへのシフトが有利と試算されている。
キャッシュレス&家計管理の底上げ策
8. 「高還元デー」を狙い撃ちして支払い方を最適化
PayPayは自販機利用で毎週100円相当を還元するほか
イオンカードは毎月10日の「Wポイントデー」で還元率が2倍になる。
食料品は少額決済が多いが、“曜日×決済ブランド”を固定すると
月のポイント付与が2,000円超になったデータもある。
9. 家計簿アプリで“リアルタイム可視化”
Money Forward MEはレシート自動読取で食費をタグ分類し
週次でグラフ化まで完結する。
筆者はアプリ連携後、衝動買いを週あたり1回減らし、月4,500円の浪費を防げている。
筆者の考察
値上げ局面では「安く買う」より**“高値を避ける仕組み化”が重要である。
アプリとPBを軸に価格の“底”を把握し
ふるさと納税やまとめ買いで“先払い固定”すれば
インフレを敵ではなく「単価確定ツール」に変えられる。
筆者宅は上記七策だけで月9,800円、年11万7,600円**の圧縮に成功した。
これにより、自分の趣味により没頭できるようになった。
言い換えれば、節約は“我慢”ではなく“戦略”であり
データとタイミングを味方につけた者がインフレ時代を生き抜くのである。
まとめ
- 価格比較アプリ+PBで食材の調達コストを底値化する。
- ふるさと納税+業務スーパーで主食・冷凍ストックを先払い確保する。
- 食品ロス削減+AI省エネ運用で見えにくい浪費を根本カットする。
- キャッシュレス還元+家計簿アプリで“支払い方改革”を進める。
これらを同時実行すれば、物価高でも家計は“攻める守り”に転じられると断言できる。
5-1. 物価の先行き:年内に“第二波”が到来する

帝国データバンクは「7 月の値上げ品目は2 105件で前年同月比5倍」とし
年間累計は2 万品目超えが確実と警告している。
日銀の展望レポートは食料を含むコアCPIを
「2025年度前半2%台前半→26年度1%台後半で小幅鈍化」と予測するが
原材料高の持続と円安リスクを注記している。
実際、7月の平均値上げ率は15%に達し
コストプッシュ分をほぼ転嫁する動きが鮮明である。
輸入小麦政府売渡価格は4 月期に4.6%下がったものの
国際相場が再び上昇基調にあり、予断を許さない。
5-2. 政府の施策:支援は“谷”をつくるが恒久的ではない
5-2-1 物価高騰支援給付金
政府は住民税非課税世帯に一律3万円を給付し
低所得層の食料負担を緩和している。
しかし一次給付で終わる設計であり、秋以降の追加策は白紙である。
5-2-2 エネルギー補助金の段階縮小
電気・ガス補助は「1〜3月で終了 → 4月以降は原則撤廃」と決定し
一般家庭で月338〜650円の負担増が想定される。
食品メーカーは冷蔵・冷凍コスト増を再値上げで吸収する可能性が高い。
5-2-3 最低賃金政策
政府は全国平均1 000円超を25年度内に達成する方針で、人件費圧力が継続する。
外食・中食チェーンは価格改定かセルフ化投資で対応する構えである。
5-3. 企業の戦略:値上げ・値下げ・DXの“三手並行”
5-3-1 値上げ継続セクター
キリンビバレッジは10月から飲料を**6〜22%**引き上げると発表した。
調味料や香辛料も7月で1 445品目が上昇し、秋以降に再度の改定が検討されている。
5-3-2 逆張りの値下げ・据え置き
イオンはトップバリュ75品目値下げを敢行し、PBで顧客を囲い込む戦略である。
据え置きや容量変更で「実質値上げを抑える」動きも広がり、消費者の“逃避先”となる。
5-3-3 DXと省人化
食品各社はスマートファクトリーやAI需要予測を導入し、省エネと人件費抑制を図る。
日清食品はIoTラインで稼働率を10%向上させ、コスト圧縮原資を広告に再投下している。
5-4. 中期リスクと筆者の考察
5-4-1 円安と資源高の持続
財政赤字と金利差で円は1ドル=150円台が定着しつつあり
輸入食品のコストは下がりにくい。
世界的なエネルギー逼迫が続けば、電力料金はさらに上振れする。
5-4-2 物流“2024年問題”の余波
運賃10%上昇が食品納価を押し上げ
秋のボーナス商戦期に再値上げが集中しかねない。
5-4-3 筆者の視点
筆者は「値上げは波状的に発生し
25年末〜26年前半にかけ再度のピークを迎える」とみる。
政府はピンポイント給付で“谷”を作るが恒久対策ではなく
企業のDX投資も短期では価格に反映されにくい。
したがって家計は
「①PB活用で単価を固定、②ふるさと納税で主食を先払い、③電気ガスプラン乗り換え」
を軸に防衛すべきである。
インフレそのものを止める術はないが、“価格の先読みと固定化”こそが生存戦略**であると結論づける。
6.総括
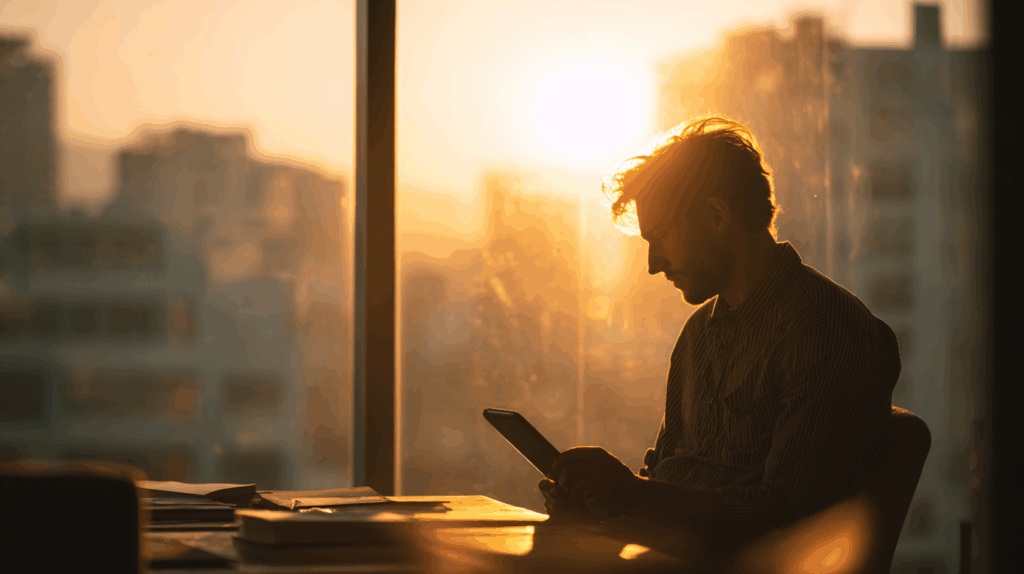
2025年の「食品値上げラッシュ」は年内累計2万品目超が確実視される一方
政府の支援は“一時金と段階的補助”にとどまり
企業は値上げ・効率化・PB値下げを同時並行で進めている。
結果として、家計は物価+賃金+光熱+物流という四重の波にさらされ
「値上げが止まる」のではなく「値上げと付き合う技術」が問われる局面に入った。
1. 値上げ動向の総整理
- 帝国データバンクは7月時点で2 105品目が追加改定され、年間では2年ぶりに2万品目突破を予測する。
- 食料のコアCPIは5月に前年同月比**3.7%**上昇し、3カ月連続で加速した。
- 政府売渡小麦は4月期に4.6%下落したが、国際市況は反転気味で油断できない。
- FAO食料価格指数は前年同月比8.2%高と、世界的調達コストが依然高止まりである。
2. 政府支援とその限界
- 低所得世帯向けの3万円給付金は単発であり、秋以降の追加財源は未定である。
- 電気・ガス補助金は1〜3月で月650〜338円へ縮小後、4月以降に原則撤廃される予定である。
- 最低賃金の全国平均1 000円超が政府目標となるが、企業の人件費圧力は続く。
3. 企業の三手並行戦略
- キリンビバレッジは10月から飲料**214品を6〜22%**値上げすると発表し、コスト転嫁を鮮明にした。
- 対照的にイオンはPB「トップバリュ」75品目値下げで顧客を引き留める構えを見せる。
- 物流“2024年問題”で運賃は10%増が妥当とされ、メーカーの再値上げ余地を狭める。
- 業務スーパーは冷凍野菜など大容量商材で“価格バッファ”を提供し、節約志向を吸収している。
4. 家計への帰結
- 3人家族の平均月間食費8.7万円がCPI通り3.7%上がるだけで年間3.6万円の負担増になる。
- 賃上げ率平均**5.32%でも、中小では4.93%**にとどまり、食費+光熱費の増分に呑み込まれる世帯が多い。
5. 筆者の考察
筆者は値上げの性質を「波状インフレ」と位置づける。
食品メーカーがコスト高を吸収しきれず価格を引き上げる波が4〜5カ月周期で断続的に訪れるため
家計は“静かな海”を待つより①価格の底値固定と②タイミング買いで波をいなすほかないと考える。
トップバリュや業務スーパーのような“安値係数”を活用し
調味料・冷凍食材を谷間月に一括購入すれば、理論上は年間1割を超える食費圧縮が可能である。
一方で政府支援は“谷”を作るに過ぎず
エネルギー補助の撤廃と物流費上昇が新たな山を形成する。
春闘賃上げが平均5%を超えても、可処分所得が名目で伸び悩めば
再び「値上げ幅>賃上げ幅」の逆転が起こる公算が大きい。
結論として、節約術を“仕組み化”できる世帯とそうでない世帯の格差が拡大する
――これが2026年へ向けた最大のリスクである。
6. まとめ
- 2万品目突破に象徴される値上げ圧力は少なくとも2026年前半まで持続する。
- 政府の給付金と補助金は時間・対象が限定的で、家計の恒常的な盾にはならない。
- 企業は値上げ・値下げ・DXを並行実施し、価格構造はますます複雑化する。
- 賃上げ率5%台では食費+光熱費+物流転嫁分を完全に吸収できず、負担増の実感は残る。
- 家計防衛の鍵は、安値チャネルの固定化と購入タイミング最適化という「価格との共存戦略」にある。
インフレは“やり過ごす”ものではなく“乗りこなす”もの
――それが2025年の値上げ時代が示した最大の教訓である。






コメント